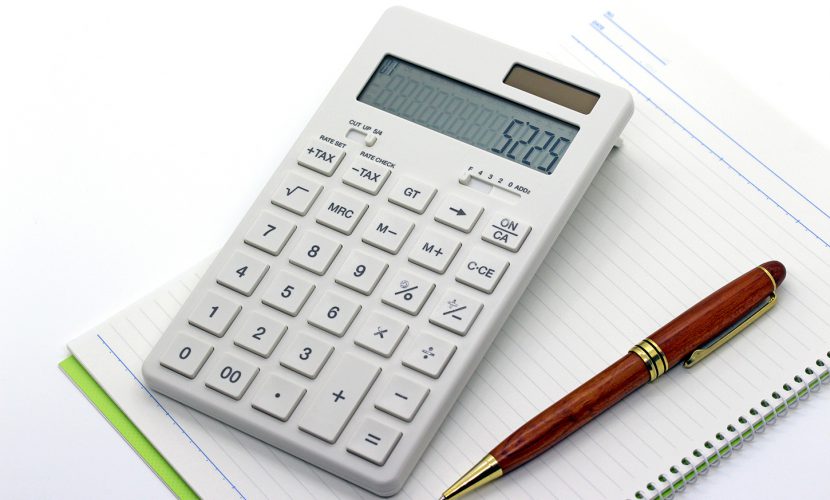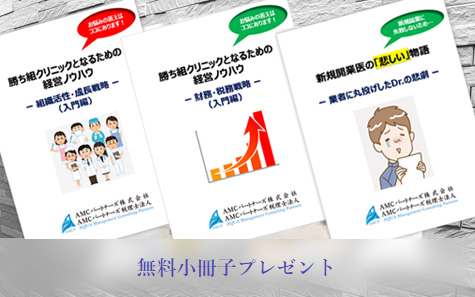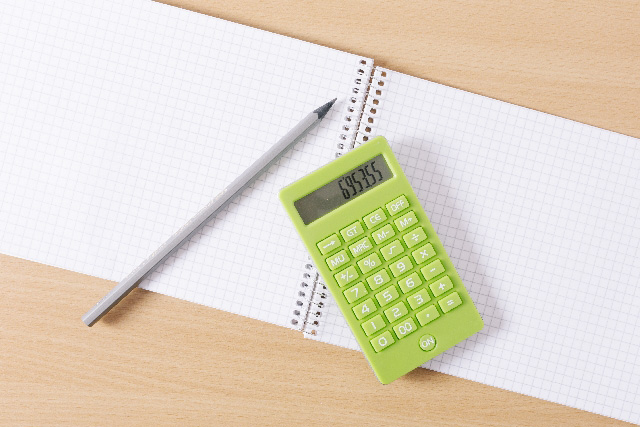今号では、iDeCo(及び企業型DC)と「退職所得控除」の関係について解説して参りします
iDeCo等と退職所得控除
前号の税制改正大綱のお話の中でも触れましたが、iDeCo(及び企業型DC、以下「iDeCo等」)の5年ルールが10年に延長されます。
そもそもiDeCoとは「確定拠出年金」のうち個人が負担するものをいい、会社が負担するものを企業型DCといいます。掛金や積立期間などに違いがありますが、「拠出時」・「運用時」・「受取時」に税制優遇を受けられること、また原則60歳まで受け取れない点などは共通です。
さて、今回のメインはその受取時の話になりますが、iDeCo等の受取り方には「一時金」方式と「年金」方式(もしくはその併用)があり、一時金として受け取った場合には退職所得として扱われ、退職所得に対する所得税が課されることとなります。
この際、税負担を軽減するために「退職所得控除」という控除規定が設けられているのですが、iDeCo等とは別に、勤務先から退職金が支払われる場合、支給時期によって控除できる金額が異なります。
基本的な考え方として、iDeCo等の一時金に係る加入期間と、勤務先からの退職金に係る勤続年数が重複している場合、重複期間についてはどちらか一方からしか退職所得控除を引くことができないのですが、一定期間の経過を要件として両方からの満額控除が認められることになっており、この期間が、iDeCo等を先に受け取るか、勤務先の退職金を先に受け取るかで次の通り変わってきます。
(1)iDeCo等を先に受け取った場合…受け取った年から5年間
| 受給年 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 |
| iDeCo等 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整 | 調整不要 |
(2)退職金を先に受け取った場合…受け取った年から20年間
| 受給年 | 2年目~20年目(19年間) | 21年目 |
| 退職金 | 調整 | 調整不要 |
上記の制限を、俗に(1)「5年ルール」・(2)「19年ルール」と呼ぶのですが、今回の改正により、(1)の期間が5年⇒10年に延長されます。
| 受給年 | 2年目~10年目(9年間) | 11年目 |
| iDeCo等 | 調整 | 調整不要 |
これにより、従来は60歳でiDeCo等の一時金を受給し、65歳で退職金を受取った場合、両方で満額の退職所得控除の適用が可能だったものが、70歳まで間を空けなければならなくなりました。
一般の従業員については、重複期間は基本的にどちらか一方でしか控除は受けられなくなったと考えてよいでしょう。
この改正は令和8年1月1日以降に支払いを受けるiDeCo等から適用されます。
なお、上記の「10年ルール」・「19年ルール」は、一方がiDeCo等である場合の制限で、両方が退職金(複数ヶ所勤務で2ヶ所以上から退職金を受給)の場合には、5年ルール(数え方は同じ)が適用されますのでご留意ください。
次に、具体的にどういった調整になるかですが、考え方自体は単純で、重複期間に対応する退職所得控除の額を、後から受け取る退職金・iDeCo等に係る退職所得控除の額から差引くことになります。
とはいえ、ここからの計算が少々難解です。
まず退職所得控除の金額ですが、勤続年数に応じて、以下の算式で計算します。
- 20年以下…40万円✕勤続年数
- 20年超……800万円+70万円✕(勤続年数-20年)
要約すると、20年以下なら年40万円、超えた期間は年70万円控除できる、という算式です。
なお、ここでいう勤続年数とは、退職金はそのまま勤続年数ですが、iDeCo等は加入期間を指します。そのため、両者の勤続年数には差がでることが多々あります(そもそも会社員がiDeCoに加入可能になったのが2017年以降ですから)。
例を挙げて計算すると、
◯ 60歳でiDeCoを先に受給(加入期間10年、300万円)
◯ 65歳で退職、退職金を受給(勤続年数40年、2,000万円)
というケースの場合、
(1)iDeCo受給時
給付額300万円に対し、控除が40万円✕10年=400万円なので所得税は課されない(100万円控除枠が余る)。
(2)退職金受給時
退職金にかかる本来の退職所得控除は、800万円+70万円✕(40年-20年)なので2,200万円(ただし、前述の通りiDeCoで300万円分控除枠を使っています)。
それでは、ここからどう計算するのか?という話ですが、何となく40年から10年を引くのかな、と思ってしまいそうですが・・・ここで「みなし重複期間」という考え方が出てきます。
これは、簡単にいえば金額ベースで何年分控除枠を使ったかという考え方で、今回のケースだと1回目の退職所得(iDeCo解約)で使用したのは300万円ですから、年40万円の控除枠から考えると300万円÷40万円=7年分(年未満切捨)の控除枠を使ったとみなし、さらに、その年数を元に使用済みの控除枠を再計算して40万円✕7年=280万円となり、本来の控除枠2,200万円-調整額280万円で1,920万円が退職金から引ける退職所得控除の金額となります。
非常にややこしいですね。もちろん、計算方法を覚えていただく必要はありませんが、今後iDeCoを受給して10年以内に退職金を受け取った場合、一定の調整があること、それにより退職金の所得税負担が増えていることは、ご承知おきください。
※ただし、退職所得控除後の1/2課税は健在ですので、改正後も退職金での受取りの節税効果が高いことに間違いありません。
なお、最初の方で述べた通り、iDeCo等は「年金」での受取も可能で、その場合には退職所得ではなく「雑所得」となり「公的年金等控除」が受けられます。基本的にはこちらの方が税負担は低くなりますが、健康状態や資金繰りなどにも考慮し、一時金と年金の併用なども含め、なるべく早期に受取計画を立てていくことが肝心です。