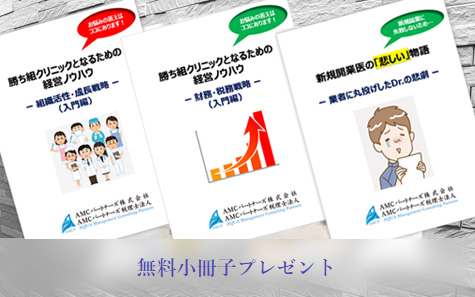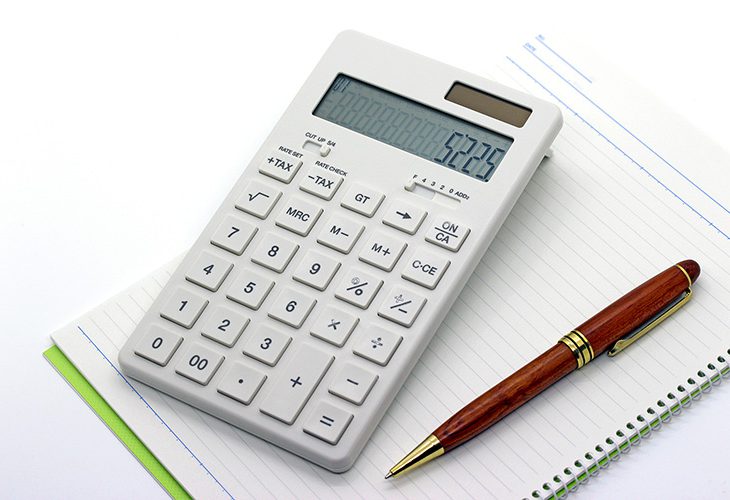今回は、今月1日に施行された税制改正法より「基礎控除の引き上げ」と、先月18日に国土交通省より公表された「公示地価」について解説していきます。
1.基礎控除の引き上げ
4月1日施行の税制改正法により、所得税の基礎控除が次の通り引き上げられました。
(1)基礎控除
合計所得が2,350万円以下の場合に、基礎控除が10万円プラスされ48万円⇒58万円に引き上げられました。
(2)加算特例
所得金額に応じ、58万円にそれぞれ次の金額が加算されます。
①所得132万円以下の場合 +37万円 (計95万円)
②所得336万円以下の場合 +30万円 (計88万円)
③所得489万円以下の場合 +10万円 (計68万円)
④所得655万円以下の場合 + 5万円 (計63万円)
ただし、恒久的な引き上げは①のみで、②③④の加算は令和8年までの2年間の時限措置とされています。
(3)給与所得控除
年収が190万円以下の場合の最低保証額が55万円⇒65万円に引き上げられます(190万円超の方は変更ありません)。給与所得控除の最低保証65万円と、基礎控除の①95万円を併せて160万円までは所得税がかからないことになります。
(4)「特定扶養親族の基準引き上げ」 と 「特定親族特別控除」
特定扶養親族(19歳から22歳までの親族)が扶養となる収入のラインが103万円⇒150万円に引き上げられます。また、150万円を超えた場合でも、控除額がいきなりゼロにならないよう「特定親族特別控除」という控除が新設されます。これにより、年収188万円までは段階的に逓減しながら控除ができるようになりました(63万円~3万円の間で10段階)。
また、「特定親族特別控除」は住民税でも併せて新設されます。
さて、では次に上記の改正の実質的な効果を考えていきましょう。
(5)住民税の年収の壁は「110万円」
今回、住民税の基礎控除については据え置かれた(最低保証額は10万円引き上げ)ため、地域差がありますが、年収が110万円を超えると住民税(10%)が課税されることとなります。
仮に160万円までフルで働いた場合、後述する社会保険料等を控除したとして、年間約3万円前後の住民税がかかることになります。
(6)社会保険「106万円・130万円の壁」も変わらず
社会保険の加入要件についても改正はありませんので、年収が130万円を超えると加入義務が生じることとなります(被保険者数が51名以上の事業所については106万円)。
壁を超えると一気に年間19~20万円程度の負担増となります。
ただし、社会保険については2026年10月の「106万円の壁」撤廃など順次加入義務者の範囲を広げる予定となっているため、いずれにせよ負担増は時間の問題です…。
なお、130万円の壁は学生であっても対象となるため、基礎控除枠が引き上げられたからとバイトを増やすと、うっかり親の扶養から外れるということが無いようくれぐれも注意が必要です。
(7)夫の勤務先での「扶養(配偶者)手当」にも注意
各企業が設ける扶養(配偶者)手当も、当然ながら税制改正と連動するとは限りません。支給条件として、やはり103万円や130万円を基準としている企業が多く、事前の確認が必要でしょう。
以上まとめると、高所得者には恩恵がなく、中間層にとっても年間2~3万円程度の減税効果で、2年限定の時限措置が外れると、それ以降はさらに1万円程度目減りすることになります。
昨年は定額減税があったこともあり、短期的にはむしろ負担増になる人も少なくないでしょう。
また、2022年~2024年の物価上昇による負担増は一世帯あたり年間28万円に昇るとの試算もあり、インフレ対策としては効果に乏しいとの見方が一般的です。
上述の通り、社会保険など他の「年収の壁」は変わっていないため働き控えによる人手不足への効果も限定的と思われます。
なお、今回の改正による減税は令和7年分からの適用ではありますが、成立が3月末ということもあり、年中の源泉所得税は従来通り計算し、年末調整又は確定申告で調整が行われることになります。
2.公示地価
3月18日、令和7年の公示地価が発表されました。
(上昇率:%)
| 全用途平均 | 住宅地 | 商業地 | |||||
| R6年 | R7年 | R6年 | R7年 | R6年 | R7年 | ||
| 全国 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | |
| 三大都市圏 | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 5.2 | 7.1 | |
| 東京圏 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 8.2 | |
| 大阪圏 | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 5.1 | 6.7 | |
| 名古屋圏 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 3.8 | |
| 地方圏 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 地方四市 | 7.7 | 5.8 | 7.0 | 4.9 | 9.2 | 7.4 | |
| その他 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
≪動向≫
(1)全国
全用途平均、住宅地、商業地のいずれも4年連続で上昇し上昇幅が拡大しています。
(2)三大都市圏
同じく、いずれも4年連続で上昇し上昇幅が拡大しています。
ただし、訪日需要の弱い名古屋圏は上昇幅がやや縮小しました。
(3)地方圏
いずれの用途も4年連続で上昇しています。
地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)の上昇率はやや縮小しましたが、その他の地域では概ね上昇率の拡大傾向が継続しています。